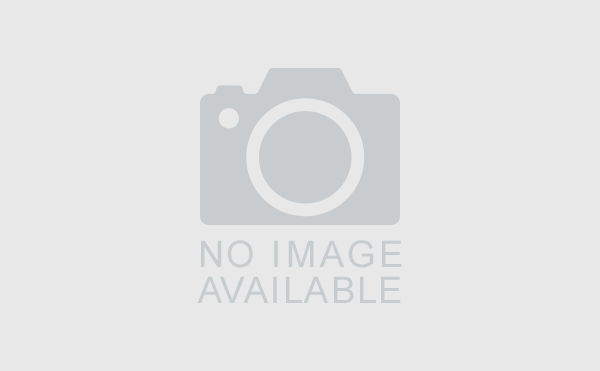第59回 中国の「外国の法律と措置の不当な域外適用の阻止についての弁法」のポイント
概要
2021年1月9日に「外国の法律と措置の不当な域外適用の阻止についての弁法」が公布、施行された。本弁法は、まだ本格的に運用されている状況ではないが、本格的な運用が始まれば、中国所在の日系企業において報告義務の履行や禁止令の順守が必要となり、日本企業においては本弁法に基づく損害賠償義務を負う可能性が生じる。
1.はじめに
2021年1月9日、商務部が「外国の法律と措置の不当な域外適用の阻止についての弁法」1(以下、「本弁法」)を公布し、本弁法は同日に施行された。本弁法は、その名称のとおり、外国の法律と措置がもたらす不当な域外適用について、これを阻止することを目的としたものであり、昨今の米中摩擦におけるアメリカ側への対抗を意識して制定されたと思われる。今後、米中摩擦が益々激化すれば、外国の貿易関連の法律等を本弁法の適用対象とすることも十分に想定され、そうなれば、日本企業や中国所在の日系企業にも影響が及ぶことになる。
本稿では、本弁法の内容について、(1)速やかな報告、(2)評価・確認、(3)禁止令の公布、(4)司法救済、(5)処罰制度の5つに大別し、これらの点から見た本弁法のポイント及び現在の運用状況について紹介する。
2. 本弁法のポイント
(1)速やかな報告(本弁法:第5条、第13条)
ア 報告の主体
報告の主体となるのは、中国の公民、法人又はその他の組織(以下、「中国の主体」)である。例えば、外国企業が中国で設立した外商投資企業は、中国の法人に該当し、当然のことながら報告の主体となる。しかし、実務においては実体の種類はさまざまであり、現在の概括的な規定では、多くの疑問が生まれることは避けられない。商務部のウェブサイト等を検索すると、香港、マカオ、台湾の個人及び企業は含まれるのか、外国銀行の中国における支店は含まれるのかといった主体に関する問合せが多く寄せられている。これについて商務部は回答を明確に公布していないようである。現時点では、商務部においても情報収集段階にあるものと推測される。
イ 報告を要する場合
報告を要するのは、外国の法律と措置の不当な域外適用に遭遇した場合であり、具体的には、外国の法律と措置により、第三国(地域)及びその公民、法人又は他の組織との通常の経済貿易及び関連活動が禁止又は制限された場合とされている。このように本弁法では、中国の主体と第三国(地域)の主体との間における経済貿易及び関連活動についてのみ規定しており、中国の主体と中国の主体との間については規定していない。したがって、例えば、第三国(地域)の主体が設立した中国の主体(外商投資企業等)と純粋な中国の主体の間の経済貿易及び関連活動が、外国の法律の域外適用によって禁止又は制限された場合に、報告を要するかは明確ではなく、今後の運用が注視されるところである。
ウ 報告期限
上記イの報告を要する場合に該当した後、30日以内に報告しなければならない。
エ 報告先部門
報告先部門は、国務院商務主管部門とされている。もっとも、本弁法では商務部の具体的な窓口部門が明確にされていない。商務部の対外貿易司(対外貿易部門)、外国投資管理司(外国投資管理部門)、又は今回の本弁法に関連する公式ニュースを掲載した美洲大洋洲司(アメリカ・オセアニア部門)のいずれかが窓口となる可能性がある。
オ 報告形式及びプロセス
本弁法では、報告形式及びプロセスについて具体的なことは明確にされておらず、中国の主体が「事実のとおり」に報告する必要があること、及びそれについて商務部に秘密保持を要求できることのみが示されている。このように、本弁法では、中国の主体が30日間という法定の期限内に「事実のとおり」に報告する旨の強制的な義務が規定されているものの、具体的な報告形式及びプロセスは明確にされておらず、現状において報告の義務を履行することは困難と考えられる。
カ 処罰
中国の主体が本弁法に従い関連状況を事実のとおりに報告しなかった場合には、警告が与えられ、また期限内に是正するよう命じられ、さらに情状の軽重に基づき過料に処され得ることが規定されている。
(2)評価・確認(本弁法:第4条、第6条)
商務部主管部門を筆頭とし、発展改革部門とその他の関連部門から構成される業務機構(以下、「業務機構」)が、以下の評価要素を総合的に考慮して、外国の法律と措置について不当な域外適用がなされているかの評価、確認を行う。
<評価要素>
1)国際法及び国際関係の基本準則に違反するか否か
2)中国の国の主権、安全、発展利益に及ぼす可能性のある影響
3)中国の公民、法人又はその他の組織の適法な権益に及ぼす可能性のある影響
4)その他考慮すべき要素
(3)禁止令の公布(本弁法:第7条、第8条、第13条)
ア 禁止令の内容
上記(2)における評価を経て、関連する外国の法律と措置に不当な域外適用の状況が存在することが確認された場合、「関連する外国の法律と措置を承認してはならず、執行してはならず、順守してはならない」旨の禁止令が公布される。
イ 禁止令の順守主体
禁止令の順守主体となるのは、報告の主体と同じく、中国の主体である。もっとも、当該主体についても、上記(1)アで言及したことと同様の疑問が存在する。
ウ 禁止令の期限
禁止令の期限については規定されておらず、業務機構が禁止令の中止又は取消を自ら決定することができるという規定のみである。なお、禁止令の執行期間中において、中国の主体は順守免除の申請を行うことができる。
エ 処罰
中国の主体が禁止令を順守しなかった場合には、警告が与えられ、また期限内に是正するよう命じられ、さらに情状の軽重に基づき過料に処され得ることが規定されている。
(4)司法による救済(本弁法:第9条)
ア 救済申請対象者
本弁法が規定する司法による救済の申請対象者は、1)禁止令の範囲内の外国の法律と措置を順守した当事者によって適法な権益を侵害された中国の主体、及び2)禁止令の範囲内における外国の法律に基づき下された判決、決定により損害を被った中国の主体である。
イ 救済の相手方
救済の相手方となるのは、1)禁止令の範囲内の外国の法律と措置を順守し、中国の主体の適法な権益を侵害した当事者、及び2)禁止令の範囲内における外国の法律に基づき下された判決、決定により利益を得た当事者である。ここでいう「当事者」の意味については、本弁法の文脈からするに、第三国(地域)及びその公民、法人又はその他の組織が含まれると解釈し得るが、このように解釈した場合、国際裁判管轄、国内判決の域外執行等に関わってくる。このため、これらの問題に対する整理、解決が必要になると考えられるが、本弁法の概括的な規定のみではこれらの問題に対する示唆を得ることができない。
ウ 救済内容
上記アの救済申請対象者に該当する中国の主体は、人民法院に訴訟を提起し、損害賠償を要求することができる。もっとも、司法の実務において部門規則レベルの本弁法を簡単に引用することで、人民法院の支持を得られるか否かについては改めて検討の必要があるものと思われる。
(5)処罰制度(本弁法:第13条、第14条)
本弁法違反に対する処罰については上記(1)カ及び(3)エにおいて言及したとおりであるが、これらに加えて、商務主管部門の職員が秘密保持義務に違反した場合の処罰についても規定されている。
3. 現在の運用状況
(1)禁止令の公布の有無
本弁法の施行後、本稿執筆時点(2021年4月13日)においては、本弁法に基づく禁止令は公布されていない。上記2.(1)オでも言及したとおり、現状では、禁止令公布の前提となる中国の主体からの報告形式及びプロセスも明確にされていないと言わざるを得ない。
(2)関連する報道内容
2021年3月25日に商務部が開催した定例記者会見の場において、ある記者からの本弁法に関する質問に対して商務部は、関連する外国の法律と措置の域外適用が国際法及び国際関係の基本準則に違反し、中国の公民、法人又はその他の組織の適法な権益に損害を与える場合、中国側は実際の状況及び関連する法律規定に基づき関連業務を展開し、国の主権、安全及び発展利益を固く守る旨の返答を行った。当該回答内容を見ると、本弁法が意識されているように思われ、本弁法は今後実務上用いられる可能性があることを感じ取れる。
(3)まとめ
以上のとおり、現時点では、まだ本弁法が本格的に運用されている状況ではないといえる。もっとも、本格的な運用が始まれば、中国所在の日系企業においては、報告義務の履行が求められ、仮に禁止令が公布されれば、禁止令の内容にも従う必要が生じる。また、日本企業等の外国企業においては、司法による救済の相手方として、損害賠償義務を負う可能性が生じる。このため、本弁法の今後の運用状況を引き続き注視する必要があると考える。
**********************************************
1 中華人民共和国商務部令2021年第1号、2021年1月9日公布、同日施行。
(2021年4月13日作成)
*本記事は、一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。
*本稿は、三菱UFJ銀行会員制情報サイト「MUFG BizBuddy」(2021年4月掲載)からの転載です。