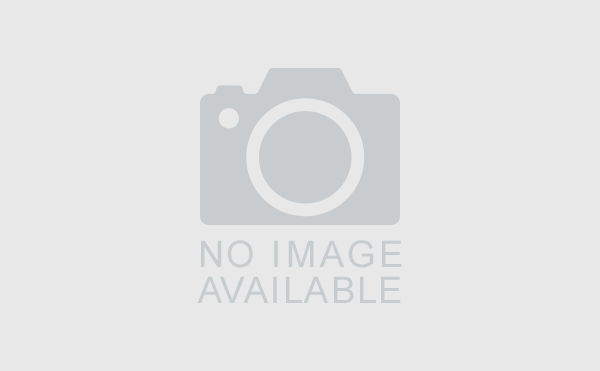第60回 中国アリババによる二者択一の独禁法違反(市場支配的地位の濫用)
概要
2021年4月10日、中国の国家市場監督管理総局は法に基づき、アリババ・グループに二者択一の違法行為の停止を命じ、かつ182.28億元の罰金を科す旨の決定を下しました。本稿では、当該処罰の経緯を説明するとともに、中国の独占禁止法における市場支配的地位濫用の法律規定の概要を紹介します。
1.処罰の経緯
2020年12月、国家市場監督管理総局は、独占禁止法1(以下、「法」)に基づき、アリババ・グループ・ホールディング(以下、「アリババ・グループ」)による中国国内のオンライン小売プラットフォームサービス市場における市場支配的地位の濫用行為について、立件し調査を行いました。
アリババ・グループは、中国国内のオンライン小売プラットフォームサービス市場において支配的地位を有し、2015年以降、当該地位を濫用してプラットフォーム内の出店者に「二者択一」を要求し、競合性を有するその他のプラットフォームにおける出店またはキャンペーンへの参加を禁じました。また、市場への影響力、プラットフォームの規則及びデータ、アルゴリズムなどの技術的手段により、さまざまな賞罰措置を講じて、「二者択一の要求が遂行されるようにした」とされています。
そして、このことが法第17条第1項第4号で禁じている「正当な理由なく、取引相手が当該事業者としか取引を行うことができないよう限定する」という市場支配的地位の濫用行為を構成するとして、2021年4月10日、国家市場監督管理総局は、アリババ・グループに違法行為の停止を命じ、かつ2019年の中国国内における売上高4557.12億元の4%、計182.28億元の罰金を科しました2。
なお、処罰決定が下される直前の2021年2月7日、国務院独占禁止委員会は、プラットフォーム経済領域における独占行為を予防及び阻止するため、「国務院独占禁止委員会によるプラットフォーム経済領域に関する独占禁止指針」3(以下、「指針」)を公布しました。指針は、基本的に法の章節、条項等に従って、プラットフォーム経済領域における適用について、1つ1つ具体的に規定しています。
2. 市場支配的地位濫用の法律規定の概要
2では、アリババ・グループの処罰事件(以下、「本処罰事件」)と法及び指針を結び付け、法が規定する市場支配的地位濫用の該当要件(関連市場、支配的地位を有すること、濫用行為)及び処罰の概要について紹介します。
(1)該当要件
ア 関連市場
関連市場の特定は、事業者が支配的地位を有するか否かを判断するための前提です。関連市場とは、事業者が一定の期間内に特定の商品またはサービス(以下、併せて「商品」)について競争を行う商品の範囲及び地域範囲を指します(法第12条第2項)。
「関連市場」の画定にあたっては、以下の通り、商品、地域及び期間の3つの要素を考慮する必要があります。
1)商品の範囲については、通常、消費者が商品間に代替可能性があると考えるか、ないと考えるかを考慮します。このような代替可能性は第1に、商品が消費者にとって同一または類似の性能、または用途を備えていることに依拠します。指針第4条第1項では、「プラットフォーム経済領域における関連商品市場の画定の基本的な方法は、代替性の分析である」と明確に規定されています。
2)地域範囲とは、事業者が特定の商品を販売した時に、当該商品と競合する商品を消費者が購入することができる地域範囲のことです。指針第4条第2項では、「プラットフォーム経済領域における関連地域市場の画定については、同様に需要代替性及び供給代替性についての分析を採用する」と明確に規定されています。
3)期間については、ある一定の期間内とされます。
本処罰事件における関連市場の三要素は、以下の通りと考えられます。
1)商品の範囲については、オンライン小売プラットフォーム事業者がプラットフォーム内の事業者及び消費者による商品取引のために提供するインターネット上の営業所、取引仲介、情報発表等のサービスにおける商品市場
2)地域範囲については、中国国内全域
3)期間については、2015年以降
イ 支配的地位を有すること
法における市場支配的地位とは、事業者が関連市場において、商品の価格、数量もしくはその他の取引条件をコントロールすることができ、または他の事業者の関連市場への参入を阻害したり、参入に影響を及ぼしたりすることができる能力を有する、市場における地位を指します(法第17条第2項)。
事業者が市場支配的地位を有することの認定は、次の各号に掲げる要素に基づかなければなりません(法第18条)4。
1)当該事業者の関連市場における市場占有率、及び関連市場の競争状況
2)当該事業者の、販売市場または原材料調達市場のコントロール能力
3)当該事業者の財力及び技術条件
4)他の事業者の、取引における当該事業者への依存度
5)他の事業者の関連市場参入の難易度
6)当該事業者の市場支配的地位の認定に関連するその他の要素
また、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、原則として、事業者が市場支配的地位を有すると推定することができます(法第19条)。
1)1つの事業者の関連市場における市場占有率が2分の1に達している場合
2)2つの事業者の関連市場における市場占有率が合計で3分の2に達している場合
3)3つの事業者の関連市場における市場占有率が合計で4分の3に達している場合
本処罰事件では、市場支配的地位を有することについて、以下の理由から認定されています。
(ア)当事者の市場占有率が50%を超える
(イ)関連市場では集中度が高く、競合者が少ない
(ウ)当事者が強い市場コントロール能力を有する
(エ)当事者が豊富な財力及び先進的な技術条件を備えている
(オ)他の事業者の、取引における当事者への依存度が高い
(カ)関連市場参入の難易度が高い
(キ)当事者が関連市場において顕著な優位性を有する
ウ 濫用行為
法第17条第1項では、市場支配的地位を有する事業者における濫用行為について全部で7項目を列挙しています。
そのうち、同条項第4号において、「正当な理由なく、取引相手が当該事業者としか取引を行うことができないよう限定すること」が挙げられています。
また、指針第15条では以下の通り具体的に細分化しており、各限定は、(ア)書面による協議の方式、(イ)電話、口頭方式による取引相手との合意、及び(ウ)プラットフォーム規則、データ、アルゴリズム、技術等の方面の実際に講じられている制限または障害の方式のいずれによっても実現できるとされています。
1)プラットフォーム内の事業者に対し、競合性を有するその他のプラットフォームとの間で「二者択一」を行うよう要求し、または取引相手が当該事業者と独占的取引を行うよう限定するその他の行為
2)取引相手が当該事業者の指定した事業者としか取引を行うことができないよう、または当該事業者が指定したチャネルを経由する等、限られた方式でしか取引を行うことができないよう限定すること
3)取引相手が特定の事業者と取引を行うことができないよう限定すること
本処罰事件では、濫用行為について、以下の理由から「正当な理由なく、取引相手が当該事業者としか取引を行うことができないよう限定すること」を構成すると認定されています。
(ア)プラットフォーム内の事業者に対し、競合性を有するその他のプラットフォームへの出店及びキャンペーンへの参加を禁じている
(イ)さまざまな賞罰措置5を講じて「二者択一」の要求が実行されるようにしている
(2)処罰
法第47条の規定によれば、事業者が本法の規定に違反し、市場支配的地位を濫用した場合、独占禁止に係る法執行機関が違法行為の停止を命じ、違法所得を没収し、かつ前年度の売上高の1%以上10%以下の罰金を科します。
本処罰事件では、アリババ・グループの2019年の中国国内における売上高4557.12億元の4%、計182.28億元の罰金が科されました。
3. まとめ
本処罰事件は、法施行以来、最高額の処罰事件となっています。今回の処罰を通して、国家市場監督管理総局が、巨大化したプラットフォーマーに対する独占禁止の強化及び無秩序な拡張の防止を企図していることが窺えると言ってもいいのではないでしょうか。
また、プラットフォーマーとの接点を有する企業においては、自社の権利を守る意味でも、本処罰事件及び指針を参照することには重要な意義があると考えます。
**********************************************
1 中華人民共和国主席令第68号、2007年8月30日公布、2008年8月1日施行
2 国家市場監督管理総局のアリババ・グループへの処罰についての公式文書http://www.samr.gov.cn/xw/zj/202104/t20210410_327702.html
3 国反壟発[2021]1号、2021年2月7日公布、同日施行
4 なお、指針第11条は法第18条の要件について詳細に説明していますが、紙幅の関係により掲載しておりません。
5 賞罰措置としては、(ア)キャンペーンへの支援資源を減らす、(イ)キャンペーン参加の資格を取り消す、(ウ)検索順位を下げる、(エ)プラットフォーム内事業者のその他の重大な権益を取り消す(資格等級の引き下げ、その他の提携の終了等)などが挙げられています。
(2021年7月1日作成)
*本記事は、一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。
*本稿は、三菱UFJ銀行会員制情報サイト「MUFG BizBuddy」(2021年7月掲載)からの転載です。