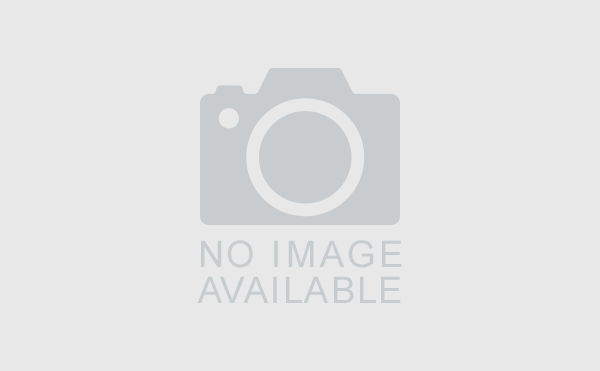第71回 改正後の中国会社法下における会社の解散・清算について
概要
2024年7月1日に施行した改正後の会社法には、会社の解散・清算に関わる内容が含まれる。本稿では、改正内容を踏まえた解散・清算における手続き等の流れを紹介する。主な流れとしては、①解散公示、②清算義務者による清算委員会の設置、公告、③債権者への通知、公告、④清算委員会による清算業務の実施、⑤清算報告書の作成、確認(清算の終了)、⑥会社登記の抹消となる。
1.はじめに
「外商投資法」1の施行後、外商投資企業の解散・清算については、主として「会社法」2に準拠することとなりました(「外商投資法」第31条)。その「会社法」は、6度目の改正がなされ、改正後の「会社法」(以下、「改正後の『会社法』」)は2024年7月1日から施行されています。改正内容には、前回「中国会社法改正による登録資本金の払込期限に関する規定」でご紹介した登録資本金の払込制度に関するものや、300人以上の従業員を有する有限会社における従業員代表董事の必置に関するものなどが含まれますが、会社の解散・清算に関わるものも含まれており、今回の改正も外商投資企業に影響が及びます。そこで、本稿では、改正後の「会社法」下での会社の解散・清算の流れについて説明します。
なお、会社の解散・清算に関連する法令としては、「会社法」以外に、「市場主体登記管理条例」3、「企業抹消指南(2023年改訂)」4、および「『会社法』適用の若干問題に関する最高人民法院の規定(2)」5(以下、「会社法規定(2)」)もありますので、これらについても言及します。
2.解散・清算の手続き
解散・清算における手続きの主な流れは次のとおりです。
(1)解散公示
(2)清算義務者による清算委員会の設置、公告
(3)債権者への通知、公告
(4)清算委員会による清算業務の実施
(5)清算報告書の作成、確認(清算の終了)
(6)会社登記の抹消
(1)解散公示
会社は、解散事由が生じた日から10日以内に、解散事由を国家企業信用情報公示システムにて、公示しなければなりません(改正後の「会社法」第229条第2項)。これは改正後、新たに設けられた規定です。上海市の実務状況によると、改正後の「会社法」が施行された2024年7月より、当該公示を行わない場合には、その後の清算手続きが開始できなくなりました。
(2)清算義務者による清算委員会の設置、公告
改正後の「会社法」第232条において、董事は会社の清算義務者である旨が新たに規定されています。そして、清算義務者は、解散事由が生じた日から15日以内に、清算委員会を設置させなければなりません(改正後の「会社法」第232条第1項)。
清算委員会は董事で構成されますが、会社の定款に別途規定がある場合、または株主会決議で別途指定された場合には、その他の人員(通常は弁護士、会計士など)が清算委員会の構成員になります(改正後の「会社法」第232条第2項)。構成員の人数については、特段の法規定はありませんが、上海市の実務状況によれば、最少2名で構成する必要があります。なお、改正前の「会社法」では、第183条に基づき、有限責任会社の清算委員会は株主で構成されることとされていましたが、今回の改正で、株式会社と同じく、清算委員会は董事で構成される旨に統一されました。
清算委員会は、設置の日から10日以内に、清算委員会の構成員および清算委員会の責任者の名簿を、国家企業信用情報公示システムを通じて公告する必要があります(「市場主体登記管理条例」第32条)。
(3)債権者への通知、公告
清算委員会は、設置の日から10日以内に、既知のすべての債権者に解散・清算を通知しなければならず、かつ60日以内に債権者公告を行う必要があります(改正後の「会社法」第235条、「会社法規定(2)」第11条)。債権者公告については、新聞(会社の規模および営業地域範囲に基づき、国レベルまたは会社登記地の省レベルの新聞)によって行うほか、改正後の「会社法」第235条および「市場主体登記管理条例」第32条で明記されているとおり、国家企業信用情報公示システムを利用して、オンラインで行うことも可能です。
債権者は、通知書を受領した日から30日以内に、通知書を受領していない場合は公告の日から45日以内に、清算委員会に債権の届出をしなければなりません。債権者が債権を届け出るときは、債権に関連する事項を説明し、かつ証明資料を提出しなければなりません。債権者の届出を受けた清算委員会は、債権を登録しなければなりません(改正後の「会社法」第235条第2項)。
債権の届出期間中、清算委員会は債権者に対して債務の弁済を行ってはなりません(改正後の「会社法」第235条第3項)。
会社が上記の法定期限内に清算委員会を設置して清算を開始しない場合、清算委員会を設置したものの清算しない場合には、会社の債権者、株主、董事またはその他の利害関係者は、人民法院に対し、清算を申請することができます。(改正後の「会社法」第233条、「会社法規定(2)」第7条)
今回の「会社法」の改正前から施行されている「会社法規定(2)」第18条によれば、株主が法定期限内に清算委員会を設置して清算を開始しないことにより、会社の財産が切り下がり、流失、毀損または滅失した場合、人民法院は、蒙った損害の範囲内で会社の債務に賠償責任を負うことを求める債権者の株主に対する主張を支持するとの内容が規定されています。また、改正後の「会社法」第232条第3項では、清算義務者が遅滞なく清算義務を履行せず、会社または債権者に損害を与えた場合、賠償責任を負わなければならないと規定しています。「会社法規定(2)」については特に改正がなされていませんので、現時点では、清算義務の履行がない場合、上記の内容に基づき、株主および清算義務者である董事のいずれに対しても賠償責任を追及できるとの解釈が可能であると考えます。
(4)清算委員会による清算業務の実施
ア 清算業務の主な内容
清算業務の主な内容としては、会社財産の整理、貸借対照表および財産リストの作成、清算プランの作成、債権債務の整理、人員整理、清算関連の残留業務の処理、会社を代表しての民事訴訟活動への参加、行政機関および司法機関に対する未納の過料の納付、税関および税務機関に対する未納税金の納付、清算プロセスで生じた税金の納付、発票の抹消等の各種税務処理、税務登記抹消手続き、税関登記抹消手続き、残余財産の分配、銀行口座の抹消手続きを挙げることができます。このうちのいくつかの項目のポイントについて言及します。
イ 債権債務の整理について
清算委員会による会社の債権債務の整理に関し、債権については、清算委員会は債権放棄をすることができます。しかしながら、債権放棄により、会社の財産が債務の完済に不足しないように注意が必要です。もしも、会社の財産が債務の完済に不足する事態に至った場合には、通常の解散による清算を中止し、法により人民法院に破産手続きを申請することになります(改正後の「会社法」第237条)。
また、清算開始後、株主、会社の実質的支配者が、悪意で会社の財産を処理して債権者に損害を与えた場合、人民法院は、債権者が株主、または会社の実質的支配者に対し、相応の賠償責任を負うことを求める主張を支持することとなります(「会社法規定(2)」第19条)。このため、株主または会社の実質的支配者が、会社に対して安易に(特に自己に対する債権について)債権放棄をさせた場合、他の債権者から損害賠償の請求をなされる可能性がある点に注意しなければなりません。
ウ 人員整理について
人員整理は、清算プロセスにおける非常に重要な課題です。ポイントは、従業員への説明会の日をいわゆる「Xデー」とし、この日を中心にスケジュールを組んでいくことです。具体的な実務対応としては、説明会の実施前に綿密に従業員への補償案を作成し、また労務関連問題が存在する場合にはその対策を講じること、説明会およびその後に続く各従業員との面談では合法的に従業員と交渉すること、さらに、説明会の実施後に従業員から労働仲裁・訴訟を提起された場合にはその対応を行うことが挙げられます。
従業員への補償を含め、十分な準備を行った上でXデーに臨んでいるという会社側の態度を従業員に示すことが重要です。
エ 会社を代表しての民事訴訟活動への参加について
清算期間中の訴訟について、会社が清算を終了しかつ抹消登記をするまでは、会社の関連民事訴訟は、会社名義で行い、清算委員会を設置している場合には、清算委員会の責任者が会社を代表して訴訟に参加し、清算委員会を設置していない場合には、元の法定代表者が会社を代表して訴訟に参加しなければなりません(改正後の「会社法」第234条第7号、「会社法規定(2)」第10条)。
また、清算期間中に係属している訴訟について、仮に訴訟終了前に会社の抹消登記が完了した場合、「『民事訴訟法』の適用に関する最高人民法院の解釈」6第64条に基づき、株主、発起人または出資者が訴訟当事者となります。清算期間中の判決の執行についても、仮に完済前に会社の抹消登記が完了した場合、「民事執行中に当事者変更・追加をする若干問題に関する最高人民法院の規定」7第21条に基づき、人民法院は、執行申請者が、株主または実質的支配者に対して、会社債務を連帯して完済する責任を負うよう求めたときにはこれを支持します。
(5)清算報告書の作成、確認(清算の終了)
清算委員会は、会社の財産を整理し、貸借対照表および財産リストを作成した後、清算プランを作成し、株主へ確認を求めなければなりません(改正後の「会社法」第236条第1項)。
清算委員会は、このようにして確認を得た清算プランによって清算を実施した後、清算報告書を作成し、再度、株主へ確認を求めます(改正後の「会社法」第239条)。清算報告書が株主の確認を得たとき、清算手続きは終了となります(改正後の「会社法規定(2)」第13条)。
なお、清算期間について、「会社法規定(2)」第16条に基づき、人民法院の主導で清算を行う場合、清算委員会の設置日より6カ月以内に清算を完了しなければなりませんが、自主清算の場合、特に清算期間に関する規定はありません。もっとも、清算委員会が清算を故意に遅延する場合、同規定第7条に基づき、会社の債権者、株主、董事またはその他の利害関係者は人民法院に清算を申請することができます。
(6)会社登記の抹消
清算委員会は、清算終了日より30日以内に登記機関に対して登記抹消手続きを申請しなければなりません(「市場主体登記管理条例」第32条)。
登記機関に抹消登記が許可された日に、会社の法人格は終了します(「市場主体登記管理条例実施細則」第44条)。
3.終わりに
上記のとおり、改正後の「会社法」下での会社の解散・清算の流れを紹介しました。もっとも、中国では、地域によって実務上の取扱いに若干の差異がある場合もあります。このため、事前に各地の実務状況を確認し、その実務状況に応じて、清算計画および清算スケジュールを十分に検討した上で、清算手続きに入ることが重要であると考えます。
********************************************************************************
1:主席令第26号、2019年3月15日公布、2020年1月1日施行
2:主席令第15号、1993年12月29日公布、1994年7月1日施行、最終改正2023年12月29日公布、2024年7月1日施行
3:国務院令第746号、2021年7月27日公布、2022年3月1日施行
4:市場監督管理総局、税関総署、税務総局2023年第58号、2023年12月21日公布、同日施行
5:法釈「2020」18号、2020年12月29日公布、2021年1月1日施行
6:法釈「2022」11号、2022年4月1日公布、同年4月10日施行
7:法釈「2020」21号、2020年12月29日公布、2021年1月1日施行
(2024年9月30日作成)
*本記事は、一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。
*本稿は、三菱UFJ銀行会員制情報サイト「MUFG BizBuddy」(2024年10月掲載)からの転載です。