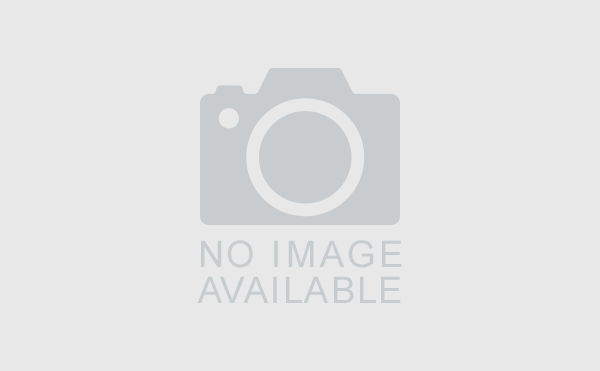第74回 「現地化」と不正の予防方法について
一、はじめに
中国市場の成熟化、中国地場企業の台頭などに加え、近時では市況の悪化もあり、中国現地法人において従前のように売上を伸ばすことが益々困難な状況となっている。その中で何とか利益を確保するためにはコスト削減が重要となる。このためもあってか、最近では、帰任する駐在員の後任者の派遣がなく、駐在員を純減させている現地法人が少なくないように感じている。コスト削減の観点からすれば、このように駐在員を可能な限り減らし、「現地化」を進めることは合理的な選択の一つといえる。
他方で、「現地化」を進めることで現地従業員のコントロールが困難となり、不正が蔓延してしまうケースも散見される。不正の発生は、「現地化」を進める企業に限ったことではないが、「現地化」を進める際には、不正をいかに予防するかを併せて検討する必要がある。そこで、本稿では、特に「現地化」を進める企業のご参考にして頂くべく、不正の予防方法のポイントをご紹介する。
二、不正の予防方法について
1. 体制整備
まずは不正を予防するための体制の整備を行うことが考えられる。
この点についての主なポイントは2点であり、1点目は権力の集中を避けることである。
一人又は一部の経営層、従業員に権力が集中している場合、これらの者に対して意見を言える者がいなくなり、また多方面からの検討、考慮の機会が失われることにより、横領行為、不正な自己取引行為、その他意識的又は無意識での法令抵触行為が行われるリスクが高まることになる。このため、権力の集中は避けるべきである。
2点目は、社内にコンプライアンス対応を専門とする部門を設置することである。当該部門に与える具体的な役割としては、例えば、次のようなものが考えられる。
①社内規則案の制定
②対外情報(各種法令、規制、他社の不正事例等)の収集及び分析
③監視活動(従業員の社内規則順守状況等の確認)
④発生した不正事例の調査、処罰案の検討
⑤コンプライアンス研修の実施
⑥内部通報制度の管理
⑦董事、総経理等の経営層及び親会社への報告
2. 社内規則の制定
次に、社内規則の制定が挙げられる。社内規則は、経営層、コンプライアンス部門が思い描く、不正予防のためのコンプライアンス体制を現地従業員に伝える手段となる。
名称は問わないが、就業規則とは別途、コンプライアンスに関する内容のみを定めたコンプライアンスマニュアル等を制定すべきである。
しかし、単にコンプライアンスマニュアル等を制定したとしても、これを遵守すべき従業員が、その内容を理解していないようであれば意味がない。
このため、制定時には、従業員にも制定過程に関与させ、議論をさせることがポイントとして挙げられる。また、制定する内容については、従業員が各自の業務を行う際の行動規範とできるように可能な限り具体的なものとし、不正行為として禁止される行為類型も提示することが望まれる。
さらに、制定後の随時のアップデートも重要であり、後述する内部監査の結果や、不正が発生してしまった場合の反省点を踏まえて、より効果的なものにアップデートしていくべきである。
3.内部通報制度の導入
続いて、内部通報制度の導入である。予防という観点からいえば、内部通報制度の導入によって、不正に対する抑止効果を期待できる。
内部通報制度の導入にあたっては、どのような仕組み(パターン)とするかがポイントである。パターンとしては、以下のものが考えられる。
パターン1:現地法人の社内窓口のみ(現地法人で完結)
パターン2:日本本社の社内窓口を(も)設ける(日本本社が関与)
パターン3:社外窓口を(も)設ける(社外の法律事務所等に依頼)
パターン1については、現地法人の内部通報制度の担当者ないしは経営層が通報対象となっている場合に通報の隠蔽がなされうること、また嫌がらせ、報復を恐れて通報の躊躇が生じうることが懸念される。このため、可能な限りパターン2又はパターン3を採るべきであるが、通報にはコンプライアンスとは無関係の内容など雑多なものも含まれる。したがって、日本本社として重要なものに絞った対応を望むようであれば、パターン3を採用し、重要なものに限り、社外窓口から日本本社に報告させる仕組みを採ることが考えられる。
なお、ここでは指摘にとどめるが、通報内容の日本本社(域外)への提供時には、中国の個人情報保護法に対する考慮も必要となる。
4.内部監査
最後に、内部監査である。内部監査では、会社運営、従業員の勤務状況、主要取引等の実態を把握した上で、把握した実態について、その合法性、構築された制度との整合性等の精査を行うこととなる。これにより、不正行為の発見はもとより、内部監査を行うこと自体が、不正行為に対する抑止力となり、予防の効果を発揮すると考える。
内部監査における実態の把握は、主として①書類調査と②ヒアリング調査によって行われる。実態を把握した後、その内容を精査し、監査報告書を作成した上で、監査報告会を実施する。
なお、仮に不正行為が発覚した場合には、更なる不正調査を実施するなどの事後対応を行うことになる。
三、おわりに(不正発生時の対応等)
以上が、不正の予防方法についてのポイントである。「現地化」によってコスト削減を図ろうとしたものの、従業員の不正(支払う必要のない支出の増加など)によってコストが増加したり、不正(取引の機会を奪うなど)によって売上が低下してしまうのでは元も子もない。「現地化」を進めるにあたっては、不正の予防が十分にできているかを併せて検討することが必須である。
以上
*本記事は、一般的な情報を提供するものであり、専門的な法的助言を提供するものではありません。また、実際の法律の適用およびその影響については、特定の事実関係によって大きく異なる可能性があります。具体的な法律問題についての法的助言をご希望される方は当事務所にご相談ください。